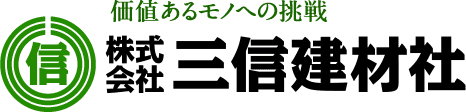かわらばん
毎月お楽しみに。
寝台特急
2009-03-01
先月ドライブ中に、3月13日の寝台特急列車「富士」の乗車券は、発売開始後10秒で売り切れたとのニュースを聞いた。
この日の乗車券は、日豊本線を経由して、東京駅を終着駅とする 寝台特急「富士」の最後のさよなら運行のチケットである。近年の風潮からして寝台車が廃止になることは、仕方のないことだとは思いながらも、自分がよく利用した方の部類に入るかどうかは分からないが、少し寂しいものがある。
寝台車に初めて乗ったのは、1969年(昭和44年)2月になって間もない頃だった。
この日の乗車券は、日豊本線を経由して、東京駅を終着駅とする 寝台特急「富士」の最後のさよなら運行のチケットである。近年の風潮からして寝台車が廃止になることは、仕方のないことだとは思いながらも、自分がよく利用した方の部類に入るかどうかは分からないが、少し寂しいものがある。
寝台車に初めて乗ったのは、1969年(昭和44年)2月になって間もない頃だった。
受験の為の東京行きだったが、何号に乗ったかは記憶にない。ただ、B寝台3段のうち下段であった。そして、静岡を過ぎたころ寝台をたたみ、うまく座席と背もたれに組み立てなおす車掌さんの手際のよさが印象に残っている。又、富士山がくっきりとよく見えたことである。
その後学生時代は、専ら夜間急行列車を利用し、寝台車は贅沢な乗り物であった。しかし、まだまだ飛行機が大衆的でなかった時代に、寝台車は贅沢な乗り物であったけれど、身近な親しみのある存在であった。
社会人になって寝台車を利用する機会は、ほとんどなかったが久々に利用する機会が訪れた。確か1985年(昭和60年)秋、職場の慰安旅行で鹿児島に行ったときだった。列車名は覚えていないが、その寝台車には、鹿児島本線久留米駅を午前0時頃に乗り込んだ記憶がある。
寝台特急「富士」に始めて乗ったのは、1995年(平成7年)12月だったと思う。東京研修のため、中津駅・東京駅間を往復利用したものだった。もうその頃は、飛行機はメジャーな乗り物であり、研修課に寝台車利用を申し込んだら、飛行機を利用するのであれば、航空チケットはこちらで手配しますが、列車利用であれば、自分で切符の手配をしてくださいとあっさり言われた。
最近で寝台車を利用したのは、平成11年6月のことである。友人と二人で熊野古道を歩こうと相談がまとまり、宇佐駅から新大阪駅まで「彗星」の利用だった。その日の宇佐駅は梅雨の走りかドシャ降りだった。彗星も今はダイヤにない。
飛行機がメジャーな乗り物として市民権を得た今、新幹線や車以外の移動手段として、寝台車を頭に思い描く人は、そうは居るまい。
しかし、寝台車のお世話になり、鉄道での旅が苦痛でなくむしろ道中の時間を楽しむタイプの人間にとって、いささか寂しい限りである。
その後学生時代は、専ら夜間急行列車を利用し、寝台車は贅沢な乗り物であった。しかし、まだまだ飛行機が大衆的でなかった時代に、寝台車は贅沢な乗り物であったけれど、身近な親しみのある存在であった。
社会人になって寝台車を利用する機会は、ほとんどなかったが久々に利用する機会が訪れた。確か1985年(昭和60年)秋、職場の慰安旅行で鹿児島に行ったときだった。列車名は覚えていないが、その寝台車には、鹿児島本線久留米駅を午前0時頃に乗り込んだ記憶がある。
寝台特急「富士」に始めて乗ったのは、1995年(平成7年)12月だったと思う。東京研修のため、中津駅・東京駅間を往復利用したものだった。もうその頃は、飛行機はメジャーな乗り物であり、研修課に寝台車利用を申し込んだら、飛行機を利用するのであれば、航空チケットはこちらで手配しますが、列車利用であれば、自分で切符の手配をしてくださいとあっさり言われた。
最近で寝台車を利用したのは、平成11年6月のことである。友人と二人で熊野古道を歩こうと相談がまとまり、宇佐駅から新大阪駅まで「彗星」の利用だった。その日の宇佐駅は梅雨の走りかドシャ降りだった。彗星も今はダイヤにない。
飛行機がメジャーな乗り物として市民権を得た今、新幹線や車以外の移動手段として、寝台車を頭に思い描く人は、そうは居るまい。
しかし、寝台車のお世話になり、鉄道での旅が苦痛でなくむしろ道中の時間を楽しむタイプの人間にとって、いささか寂しい限りである。
ありがとうございました 合掌
経営管理部
樋口 修司
樋口 修司
“ゆっくり”そして“しっかり”と
2009-02-01
2008年の暮の数日間、越えようのない寂寥感(せきりょうかん)にとらわれてすごしました。
2009年を迎え、『前向きに』と、決意を新たにしています。そこで、新年から今日までに目にしたり耳にして、心に響いた文章や言葉を拾い集めてみましたので、思いや気持ちを共有していただきたいと思います。著作権に抵触しない程度に・・・。
2009年を迎え、『前向きに』と、決意を新たにしています。そこで、新年から今日までに目にしたり耳にして、心に響いた文章や言葉を拾い集めてみましたので、思いや気持ちを共有していただきたいと思います。著作権に抵触しない程度に・・・。
先ずは丑歳(うしどし)にちなんで、夏目漱石が誰かに宛てた手紙の一部です。
『牛になることがどうしても必要です。
我々はとにかく馬になりたがりますが、
牛にはなかなかなれません。
世の中は根気の前に頭を下げることを知っています。』
我々はとにかく馬になりたがりますが、
牛にはなかなかなれません。
世の中は根気の前に頭を下げることを知っています。』
次に日本に帰化した3人の対談集からです。自分の国を捨て日本人になった元外国人の3人が、日本をすばらしいと思うのは
『コツコツとひとつのことを長くやっている人を尊ぶ気風があること。』だそうです。地球上のほとんどの国や文化は、『将来は大金持になること、又は、何かわからないが偉大なことを成し遂げたい』人達の集まりなのだそうです。しかも、“大金持”とか“偉大”という気概(きがい)を口に出さなければ、子供の時からバカにされるとうい文化ばかりで、そのことが世の中を悪くしている、と彼等が口々に語ることを大変興味深く思いました。
創業以来60年を越えた㈱三信建材社が、2、3年後の将来といわず遠い将来も、コツコツと地域に貢献出来る社員の集まりである会社でありつづけることを願ってやみません。
『現在は、あなたが夢みた将来ですか?』これも2009年お正月に誰かが言っていて大急ぎでTVの前で書き取ったものです。いかがですか?いいお正月でした。
『現在は、あなたが夢みた将来ですか?』これも2009年お正月に誰かが言っていて大急ぎでTVの前で書き取ったものです。いかがですか?いいお正月でした。
感謝。
㈱三信建材社
監査役 影木正子
新年のご挨拶
2009-01-01

あけましておめでとうございます。
昨年を表す漢字として「変」が選ばれました。
政治の変、経済の変、食品の変、気候の変、振り返れば本当に色々な変が吹き出た一年でした。
しかしながら、なんの予兆もなしにいきなり物事が変わることはないと思います。どれも、皆が「なんかまずいけど、このままでいいのかな」と思いながら頭の片隅に追いやってきただけではないかと言う思いにとらわれているところです。
お客様の価格に対する要求は厳しいものでした。しかし日本での価格要求はあくまでも安全性や品質が確保された上でのものです。価格要求を満たすことが、安全性や品質を無視しなければならないところまで来てしまってはいけないと強く思います。
また、先行きの不安感は消費の意欲をそぎ、私どもが仕事をさせてもらっている建築業界もその影響を受けずにはいられません。
だからこそ、「お取引頂く地域の建設業の皆様の繁栄があってはじめて当社は成り立つ」ということを再度認識し、お取引先の皆様が仕事を勝ち得るための商品をそして情報を提供できるようにとの思いで㈱三信建材社は2009年を迎えました。
お客様が取引する価値のある会社へと「変わり続ける」ため、社員一丸となり本年も頑張っていきたいと思っております。更なるご指導、ご鞭撻をお願いいたします。
株式会社 三信建材社
代表取締役 大家 覚(おおいえ さとる)
映画のススメ
2008-12-01
今、とても気になっている映画があります。高校時代にものすごくはまってしまい同じような著者の違う本を数冊読んでいました。今度、その映画が公開するということで、もう一度読んでみようと思い一冊開いてみたらびっくりです。文庫本だけども字が小さく1ページにぎっしりつまっていました。こんなものを、一生懸命に読んでいたんだと感心してしまいました。でも、はまっていたのだから、そんなに苦にはならなかったのかもしれません。
映画は、中国歴史のものでタイトルから「赤壁」の場面のようです。まだ、見ていませんが・・・・・・。「赤壁」は、ハイライトシーンであり、わたしの好きな場面でもあります。あの英雄が・・・、あの軍師・・・が、スクリーンで蘇るのかと思うと、想像がふくらみます。それと、日本人も出演しているようなので、タイトルがわかった人は是非、みてほしい映画です。わたしも、公開中に見に行こうかと思っています。
三信商事㈱ Y.T
三信商事㈱ Y.T
郷土史講座№12(中津 小笠原時代 №2)
2008-11-01
前回は中津 小笠原時代初代長次(ながつぐ)と2代長勝(ながかつ)を話しましたが、今回は引き続き中津 小笠原時代後半を話したいと思います。
(3) 3代 長胤(ながたね)時代~2代長勝の兄・長知(ながとも)の長子
天和(てんな)2(1682)、長胤が家督をつぐと初めの内は藩財政の立て直しに努力していました。貞享3(1686) 本耶馬溪の樋田から沖代平野まで灌漑を目的に15kmの荒瀬井路の工事を行い、又、元禄7(1694) 100軒余の中津城下の大火の復旧工事のため、莫大な費用を要し、藩財政をさらに圧迫、悪化させます。長胤も浪費・乱行癖があり、そううつ病でした。領民には苛税を課し、こうした酷政は幕府の知るところとなり、元禄11(1698)7月28日領地は没収され、長胤は小倉藩に預けられます。領地没収の翌日、譜代大名で祖父が徳川家康の血を引くこともあり、幕府は特旨をもって下毛・宇佐2郡4万石を長胤の弟である長円が城主として残ることになります。残りの領地(宇佐市、本耶馬、耶馬溪、山国の一部)は幕府直轄の天領になり、陣屋は四日市(現在の勤労青少年ホーム)にありました。長円の弟・長宥(ながます)は時枝領5,000石を分け与えられ、旗本(家禄1万石未満)になります。陣屋は豊前善光寺の門前にありました。
(4) 4代 長円(ながのぶ)時代~3代長胤の弟
長円も又、病弱で乱行が始まります。元禄16(1703) 当時の東浜村と新田村の間の松原に別荘を築きます。現在の工科短大(東浜)東側の道路をはさんだ場所で「お池州」と呼ばれていました。今は畑ですが、当時は池があり、ほとりに別荘を建てました。中津城から蛎瀬、大塚に堀を掘って城内から舟で通えるようにし、池のほとりの別荘は室内は装飾に善美をつくし、日夜の宴遊で藩財政を又もや圧迫します。38才の時、桧原山で5日間の狩りをした後、発熱し、狂乱状態になり、亡くなります。
(5) 5代 長邑(ながまさ)時代~4代長円の長子
正徳3(1713) 4才で封を継ぎますが、享保元(1716) 7才で病死してしまいます。継嗣(けいし)なく領地を没収され、中津小笠原藩は消滅します。弟 喜三郎(長興)は播州安志(あんじ)1万石(兵庫県姫路市安富町安志)の知行を与えられますが、安志藩で長興も病弱で19才で隠居、継嗣なく小倉藩より藩主を迎え、その後、小倉藩の支城の如く扱われました。
悪評のみを残した小笠原時代だと思われますが、少なくとも中津が城下町として存在を明確にしたのはこの時代であるのは確かです。
S(サンシン)著

荒瀬神社

小笠原長次の墓

小倉城

陣屋門